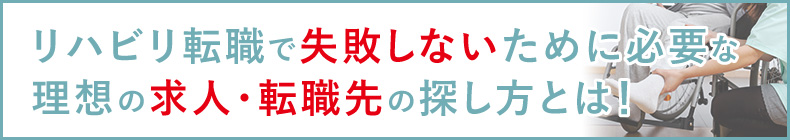言語聴覚士として勉強しておくべきこと:解剖学と脳神経
言語聴覚士(ST)の働く場として、総合病院やデイサービス、保健関連施設、教育関係施設などさまざまなところがあります。そしてそのような現場で、コミュニケーションや摂食、嚥下などの機能に障害を持った人を支援します。
このように、同じ言語聴覚士でも働く場所や求められる役割は人それぞれ違います。しかし、どのような職場や立場であっても言語聴覚士として必ず学んでおくべきことがあります。
そこで今回は、言語聴覚士として勉強しておくべきことについて述べます。
もくじ
解剖学
言語聴覚士がリハビリを行う対象者は年齢を問わず、摂食や嚥下、言語などに障害がある人が主になります。このような障害は、顔面や口腔内、喉といった首周りの器官が担っている機能に問題があることで生じます。
例えば、話すために必要な顔面の筋肉や舌が麻痺していることで発声が障害されると、スムーズに話をすることができなくなります。
このような体の機能は、その役割を担っている器官の構造が正常であるかによって大きく変わります。例えば、顔にある筋肉が損傷するなど筋肉の構造に問題が生じると、表情を作ったり口を開けたりするという筋の役割は障害されます。
言語聴覚士はそのような障害された体の機能に対して、上手く働かせることができるようになることを目標にリハビリを行います。
このとき、リハビリの効果を十分に出すためには、体の機能を理解しておく必要があります。先ほども述べたように、器官の造りが正常に保たれていることで、適切に機能することができます。そのため、まずは体の正常な構造を知っておくことが大切です。
そしてそのような体の構造を知るためには解剖学を勉強する必要があります。
以上のような理由から、言語聴覚士であれば、特に首周りに関する解剖学は誰でも勉強すべきことだといえます。
脳神経学
解剖学と同様に、脳神経学も言語聴覚士であれば必ず学んでおく必要がある分野です。
今まで述べたように、言語聴覚士がリハビリを行う対象となる人は、顔面や口腔内、喉といったような首周りの機能に障害を持った人がほとんどです。
そして、そのような顔面から首にかけての筋肉や器官の多くは、脳神経によって働きがコントロールされています。そのため言語聴覚士は、首周りの器官に関する解剖学だけでなく、それらを調整している脳神経についても詳しく学ぶ必要があります。
また、言語聴覚士のリハビリ対象となる患者さんは、大半が「脳血管疾患」に関連した診断名が付けられてリハビリが処方されます。つまり、言語聴覚士が対応するほとんどの患者さんは、脳神経系に障害を持った人になります。
以上のような理由から、言語聴覚士であれば脳神経学を学んでおくことは必須であるといえます。
今回述べたように、言語聴覚士として働く場所や求められる役割は人それぞれです。しかし、解剖学と脳神経学は、言語聴覚士であれば誰でも学ばなければいけないものです。どのような職場に転職しても困らないように、この2つの学問だけは必ず勉強しておくようにしましょう。
解剖学と脳神経学をしっかり学んでおくと、転職先の選択肢も広がるはずです。
リハビリ関係者が転職を考えるとき、転職サイトを活用するとより自分の希望に沿う求人を見つけることができるようになります。自分一人では頑張っても1~2社へのアプローチであり、さらに労働条件や年収の交渉まで行うのは現実的ではありません。
一方で専門のコンサルタントに頼めば、100社ほどの求人から最適の条件を選択できるだけでなく、病院や施設を含め、その他企業との交渉まですべて行ってくれます。
ただ、転職サイトによって特徴が大きく異なります。例えば、電話だけの対応で素早さを重視する会社があれば、面接まで同行することで難しい案件への対応を得意としている会社もあります。他には、大手企業に強みを発揮する会社があれば、地方求人を多く保有している会社もあります。
これらを理解したうえで専門のコンサルタントを活用するようにしましょう。以下のページで転職サイトの特徴を解説しているため、それぞれの転職サイトの違いを学ぶことで、転職での失敗を防ぐことができます。
注目の人気記事
管理人による転職体験記
理学療法士として、私が実際に転職サイトを利用して転職した経験を述べています。見学の際に感じたことや、失敗した経験から、転職の際に必要だと感じたことなどを詳細に記しています。
転職サイト利用の流れ
転職サイトを活用するとはいっても、初めて利用する人がほとんどなので「どのような流れで進んでいくのか分からない」という不安が残ります。実際には難しいことは何一つないのですが、どのような手順で進んでいくのかを解説しています。
転職サイトを有効活用する方法
良い求人を見つけ、転職を成功させるときは転職サイトの利用が一番の近道です。しかし、リハビリ関連職者の中でも、転職サイトを利用したことがないという人は多いです。そこで、転職サイトの有効な活用方法について記しています。